アサヒグループ工場停止から学ぶ、1台のPCが止まることの恐怖
2025.10.3延命コラム

先日、日本を代表する食品メーカーであるアサヒグループホールディングスに衝撃が走りました。サイバー攻撃によるシステム障害により、国内全30工場の生産が一時停止。受注・出荷業務が完全にストップし、復旧のめども立たない状況が数日間続いたのです。
今回のケースはサイバー攻撃が原因でしたが、製造業の現場では「1台のPCが停止する」ことで同様の事態が起こり得ます。
しかも、サイバー攻撃よりもはるかに高い確率で起こります。それは工場で稼働している古い産業用PCの故障が原因です。明日、御社の工場も同じ状況に陥るかもしれないのです。
そこで今回は、アサヒグループの事例から見えてきた「1台のPC停止の本当の怖さ」と、製造業が今すぐ取るべき予防策をご紹介します。
アサヒグループで何が起きたのか
9月29日午前7時頃、アサヒグループのシステムにランサムウェア攻撃が発生しました。この攻撃により、以下のような広範囲な影響が出ています。
国内グループ各社の受注業務が完全停止し、出荷業務も全面ストップしました。お客様相談室などのコールセンター業務も機能しなくなり、国内全30工場の生産ラインが止まりました。10月6日以降に予定されていた新商品12品目の発売が延期となり、現在も復旧のめどは立っていません。
注目すべきは、生産設備そのものは無事だったという点です。にもかかわらず、受注・出荷を管理するシステムが止まったことで、工場全体が稼働できなくなったのです。
これは製造業における制御PCの重要性を物語っています。
なぜ1台のPCでこれほどの影響が出るのか
-
製造現場では、1台の産業用PCが複数の重要な役割を担っています。
生産管理システムでは、製造指示、在庫管理、工程管理を一元的に制御しています。出荷管理システムでは、受注データの受信、出荷指示の発行、配送計画の立案を行います。品質管理システムでは、検査データの記録、トレーサビリティの確保、品質基準の管理を担当しています。設備制御PCでは、製造ラインの制御、センサーデータの収集、異常検知と停止制御を実行しています。
-

つまり、このうち1台でも止まれば、連鎖的に製造プロセス全体が停止するのです。アサヒグループのケースでは、サイバー攻撃で管理系システムが停止したため、たとえ製造設備が無事でも、「何を作るか」「どこに出荷するか」が分からなくなり、結果として全工場停止という事態に陥りました。
サイバー攻撃より高確率な「突然の故障」
今回はサイバー攻撃が原因でしたが、製造現場でより高い確率で発生するのが長年使っている産業用PCの突然の故障です。
サイバー攻撃の発生確率は年間数%程度だと思います。一方、15年以上稼働している産業用PCの年間故障率は20%程度と言われています。これが20年超になるとかなりの確率となります。
つまり、古い産業用PCを使い続けることは、サイバー攻撃を受けるよりもはるかに高い確率で今回のような問題を引き起こすリスクを抱えているということです。
実際の製造現場では、15年以上前の産業用PCが現役稼働しているケースが非常に多く見られます。それらはWindows2000、XPなどサポートが終了しているOSを使用しており、もし故障しても部品が市場で入手不可能なものも多いです。
それら古いPCの多くはメーカー保守契約も終了しており、いつ壊れてもおかしくない状態なのです。
アサヒの事例から学ぶ故障時の損害
アサヒグループの事例から、システム停止がもたらす具体的な損害を見てみましょう。
生産停止による直接損失として、国内全30工場の稼働停止により、1日あたり推定数億円の機会損失が発生しています。復旧まで数日かかれば、損失は数十億円規模に膨らみます。
サプライチェーンへの影響も深刻です。取引先への商品供給が停止し、小売店の棚が空になり、消費者が競合商品に流れる可能性があります。
ブランドイメージの毀損も避けられません。「商品が買えない」という消費者の不満が高まり、SNSでの批判的な投稿が拡散し、株価への影響も発生しています。実際、発表後にアサヒグループの株価は下落しました。
新商品発売の延期により、マーケティング計画の見直しが必要となり、販促費用の追加発生や、競合他社への機会提供といった問題も生じています。
御社の工場で起こった場合、損害額は変わったとしても同じような損害が出ると考えておきましょう。
「動いているから大丈夫」という危険な思い込み
多くの製造現場で聞かれる言葉があります。「うちのPCは古いけど、まだ動いているから大丈夫だよ」。これは非常に危険な思い込みです。
産業用PCは突然故障します。前日まで正常に動いていても、朝出社したら起動しないということは珍しくありません。ハードディスクの故障、電源ユニットの故障、マザーボードの故障は、予兆なく発生することがほとんどです。
アサヒグループのケースでも、システムは前日まで正常に稼働していました。それがサイバー攻撃をきっかけに、突然、広範囲にわたる障害となったのです。
「まだ動いている」は「そろそろ限界に近い」と読み替えるべきでしょう。特に製造から15年以上経過したPCは、いつ止まってもおかしくない状態にあります。
アサヒの教訓から導く「予防保全の重要性」
今回のアサヒグループの事例が教えてくれるのは、「システム停止は事業の継続を脅かす」という事です。原因がサイバー攻撃であれ、老朽化による故障であれ、結果は同じだと思います。
重要なのは、止まってから対処するのではなく、止まる前に対策することです。
バックアップシステムの整備により、メイン機が故障しても即座に切り替え可能な体制を構築することができます。
また、古いPCの計画的な延命により、オーバーホールで安定稼働を実現できます。段階的な更新計画により、予算に応じた計画的なシステム更新が可能になります。データバックアップの徹底により、万一の際のデータ復旧時間を最小化できます。
アサヒグループのような大企業でさえ、システム停止で大きな影響を受けました。中小規模の製造業であれば、その影響は致命的になる可能性があります。
なぜなら、他に生産拠点が無かったり、復旧に使えるが資金的な余裕が少ない事が多いからです。
「故障する前」の延命対策が最も効果的
古い産業用PCが突然故障してから対処するのと、動いているうちに延命対策を施すのでは、コストも時間も大きく異なります。
故障後の対応では、緊急の部品調達、生産停止による機会損失、取引先への信頼低下、従業員の残業代増加といったコストが発生します。
一方、故障前の延命対策では、計画的な予算確保が可能で、生産への影響を最小限に抑えられ、予防保全による信頼性向上が期待でき、長期的な安定稼働を実現できます。
オーバーホールによる延命なら、システム全更新と比較して大幅にコストを抑えながら、安定稼働が可能になります。バックアップ機の整備により、メイン機故障時の切り替えが可能になります。重要部品の予防交換により、突然故障するリスクを大幅に軽減できるのです。
明日は我が身だと考えておく事が大事
アサヒグループホールディングスのシステム障害は、サイバー攻撃が原因でした。
しかし、製造業の現場では、もっと高い確率で古い産業用PCが突然故障するという事態が発生します。
1台のPCが止まることで、全工場が停止し、数億円規模の損失が発生する。そして、取引先との信頼関係が損なわれて仕事がこなくなる。
これは決して大企業だけの問題ではありません。むしろ、中小製造業にこそ、深刻な影響をもたらします。
重要なのは、「止まってから対処する」のではなく、「止まる前に対策する」ことです。故障は予告なく突然やってきます。しかし、対策は今からでも始められます。

日本ピーシーエキスパート
今回のアサヒグループの教訓を活かし、今日から予防保全を始めていただきたいと考えてます。「まだ動いているから大丈夫」という思い込みを捨て、「動いている今だからこそ対策できる」という発想に転換してください。
古い産業用PCの延命事例をまとめた資料をダウンロードできます
-
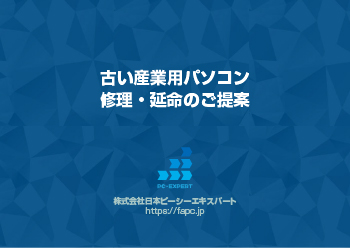
-
これまで当社で行った延命事例をPDFにまとめてご紹介しております。社内でのご検討の際にお使いください。
 資料ダウンロード
資料ダウンロード





